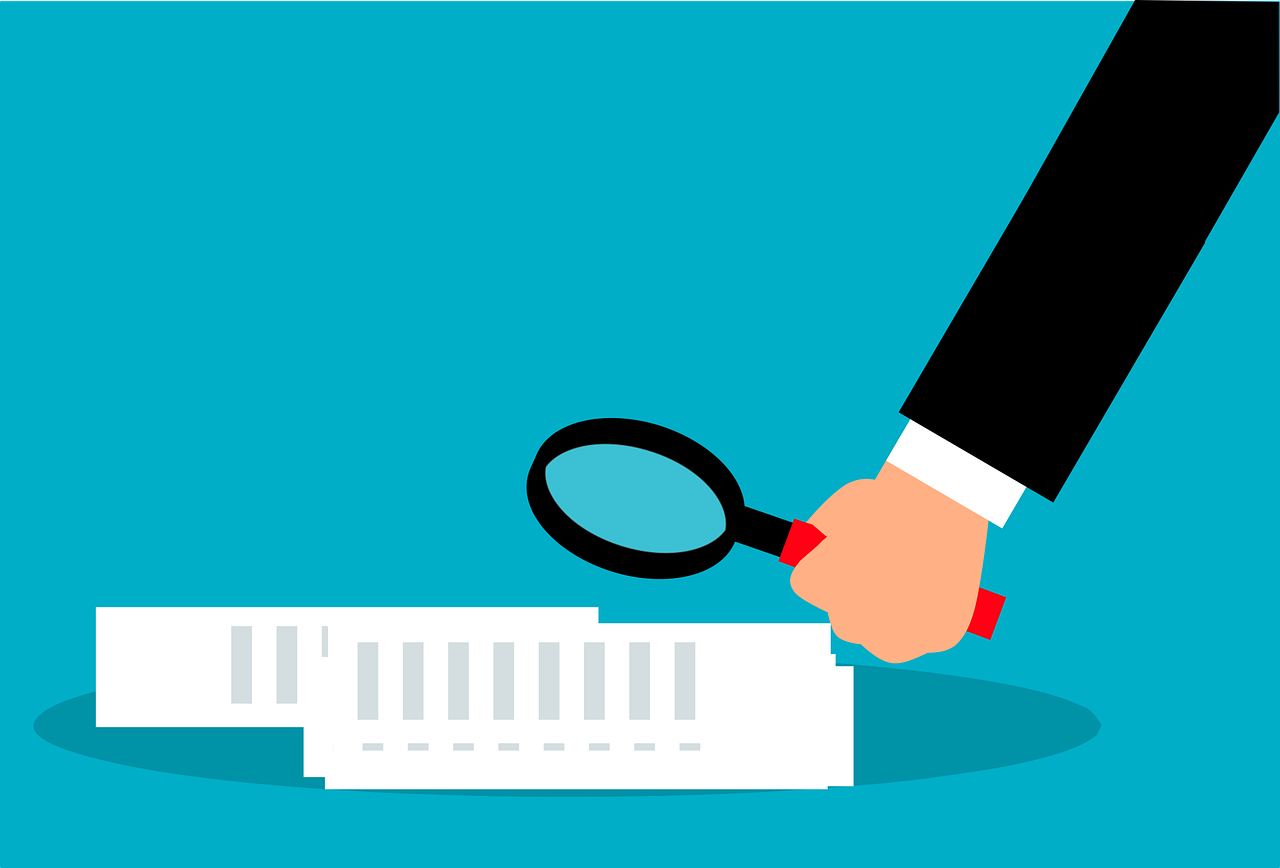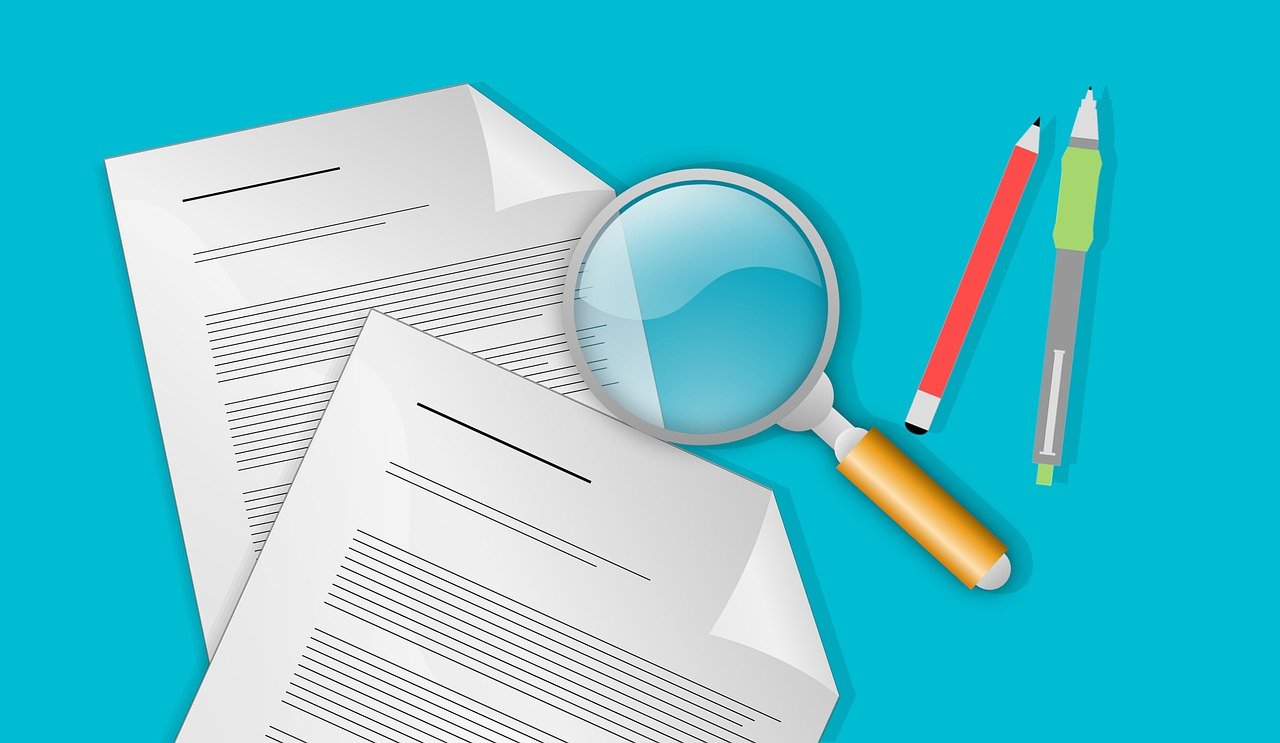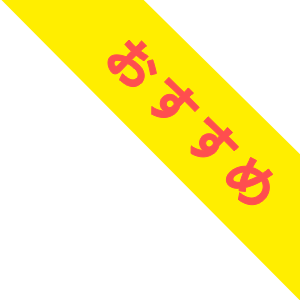目次
テレワークの定義

まずテレワークの定義を確認してみましょう。
テレワークとは、ICT(情報通信技術)を活用した働き方の総称で、勤務場所や勤務時間をとわず、インターネットを活用して遠隔地で仕事をする働き方の全般を意味しております。
テレワークの種類には、自宅で働く在宅勤務のほか、移動中の交通機関や出先のカフェなどを活用するモバイルワークや、職場から離れた場所での小規模施設を利用するサテライトオフィス、などがございます。テレワークの詳細は以下でも詳しく解説しておりますのでよろしければご参考下さい。
在宅勤務との違いは?
では、よく聞く「在宅勤務」とはなんでしょうか。
テレワークと在宅勤務、両者は同じような意味で使われることも多いですが、念のため知識として違いを押さえておきましょう。
在宅勤務は、あくまでもテレワークでの働き方のひとつの形態にあたります。
オフィスへ出社をせずに、インターネット環境を活用することで自宅で業務を行う、ひとつの業務形態です。
育児や介護などの理由で出社が困難な人、自宅から職場までの道のりが多く出勤に時間がかかる人などが、同じ職場で働き続けるための業務形態としても注目されております。
少子高齢化に伴い、生産年齢人口は減少を続けております。このような社会的課題に対応するための働き方改革としても大切な役割を果たす業務形態です。
コールセンターにおけるテレワーク(在宅化)の実態は?
コールセンター業界におけるテレワークの普及はどのくらいなのでしょうか。実態を見てみましょう。
一般社団法人日本コールセンター協会(CCAJ)が行っている「2022年度コールセンター企業実態調査」の報告では、在宅コミュニケーターの採用予定について「既に採用している」と答えた会社は50%(N=51)であったと示されています。導入の理由として最も多いのが「働き方の多様化のため」であり、次に「BCP対策のため」が続きました。
約半分の会社が在宅コミュニケーターの採用を既に実施している結果となり、急速に普及が進んでいるとは言えないものの、導入の理由を見ると、新型コロナウイルスの流行が会社の運営方針に少なからず影響を与えていることが想像されます。
将来的な人材確保、事業存続の為、柔軟な働き方を用意できるよう今から備えを進める意識が徐々に広がりを見せているようです。
※調査結果は「在宅コミュニケーターの採用予定」「在宅コミュニケーターを採用した理由(複数回答)」より抜粋
コールセンターにもテレワーク(在宅化)が必要な理由とは
前述のように、コールセンター業務においても、テレワーク(特に在宅勤務)を前向きに捉える企業が徐々に増えています。
ここでは、テレワークが必要な理由について、もう少し掘り下げて考えてみたいと思います。
BCPへの対策
一つ目は、BCP対策として在宅勤務が有効だからです。
前述のコールセンター業界のテレワーク実態でも少し触れさせていただきましたが、近年、BCP対策に乗り出す企業が増えており、コールセンター業界も例外ではありません。
背景としては、コロナによるパンデミックや、東日本大震災のような災害が起こり、通常業務を続けるのが困難になったことでこれまでの働き方を見直す機会が増えたからです。
特にコロナの流行においては、出社を控える需要も高まる中、出社を強いらなければならないコールセンターの運営体制にもどかしく思われる方もいたでしょう。
今後も感染症の流行や大きな災害が起こってしまう可能性はゼロではありません。
よって、将来的なBCP対策として、コールセンター業務においても在宅勤務に関心が集まっています。
※BCP(Business Continuity Plan)とは
日本語で「事業継続計画」を意味します。緊急時に事業が継続できなくなることに備え、事前に対策を検討することです。
人材の確保
二つ目は、人材の確保のためです。
生産労働人口が減少する中で人材の確保は企業にとって大きな課題となってまいります。
良質な人材であっても、育児や介護により自宅から離れられなくなり、急に退職をせざるを得ない状況も可能性としてはございます。
そのような事態を防ぐために、在宅勤務を活用して柔軟に働ける環境を提供し、人材を確保しておく必要があるのです。
また在宅に対応していることで、離職を低減させることはもちろん、遠方からの採用も行えるようになり、人材の幅を広げることも可能です。
ワークライフバランスへの対応
三つめは、ワークライフバランスに対応するためです。
前述しましたように、労働人口が減る中で人材を確保するためには、様々な雇用ニーズに対応していかなければなりません。
特に求職書にとって有利な状況の場合は、在宅化対応が柔軟な働き方のアピールに繋がりますので、これまで取り逃していた人材の採用も期待できます。
時代とともに人々の生き方は多様化します。
特に近年では新型コロナウイルスの影響もあり、人々の働き方や価値観は大きく変化しました。自分らしく生きようとする需要が生まれ、仕事とプライベートを両立させられるような柔軟な働き方を採用している企業の人気が高まっています。
もはや、現代の日本においては、労働者の需要を敏感にキャッチし、様々な働き方に柔軟に対応できるかどうかが今後の企業存続を左右するといっても過言ではありません。
コールセンターのテレワーク(在宅化)に管理者が抱える不安

在宅勤務のメリットや、コールセンター業務においても在宅勤務が求められる理由について解説いたしました。
一方でコールセンター業務では在宅化を進めにくいという声もございます。
ここからは、コールセンター業務の管理者とオペレーターの双方の視点から、コールセンター業務の在宅化が進まない背景をみていきましょう。
まずは、管理者の視点でコールセンターの在宅化へ抱える不安を確認してみましょう。
セキュリティリスク
コールセンター業務ではお客様個人の情報を多く取り扱うことが多いです。
電話でもお名前や生年月日、ご住所などの個人情報を伺ったり、企業の顧客管理データへアクセスしながら業務を行ったりもします。
その為、オフィスの外で業務を行うことによる情報漏えいの観点からセキュリティリスクを気にされる管理者の方は多いです。
在宅での業務のみならず、企業によっては、コールセンター業務のエリアへは私物の持ち込みを禁止したり、入退室にも制限を行ったりと、セキュリティ対策を入念にされているところもございます。
セキュリティリスクに対する不安が、コールセンター業務の在宅化が進まない背景のひとつであり、大きな要因でもあります。
オペレーターの勤怠管理や稼働状況の確認
在宅勤務では稼働状況が見えない、在宅のオペレーターとオフィスで稼働しているオペレーターが混在してしまう、といったことから、在宅勤務を取り入れることへ不安を感じる管理者の方やSVの方も多くいらっしゃるかと思います。
また離席や休憩の状況確認も、オフィスでは目視でも確認できますが、在宅では難しくなると考えられるかたもいらっしゃるようです。
オペレーターの勤怠管理や稼働状況の確認への不安も、コールセンター業務の在宅化が進まない背景のひとつです。
顧客トラブルの際の適切なサポート
顧客とのトラブルを理由に在宅化が進められないとお考えの管理者の方もいらっしゃいます。
ひとつは、顧客からのクレームなどへの対応です。在宅で対応する不安として、クレームへの対応など、適切なサポートが求められる場合などがあげられます。
また、顧客との通話中における通信トラブルを懸念される方もいらっしゃいます。通話のやり取りが途中で途切れることは顧客とのトラブルにもつながりかねません。その為、安定した通信環境について不安視される方もいます。
コミュニケーション不足によるオペレーターの精神的負担
コールセンターのオペレーターの方は様々な顧客とのやり取りを1日に何度もこなしていく必要がございます。
その為、精神的な負担をかけてしまわないか、在宅化によって孤立させてしまうことへ不安を抱く管理者の方もいらっしゃるかと思います。
精神的な負担や苦痛が続くことで、離職につながる恐れや、品質の低下を懸念されるケースです。
コールセンターのテレワーク(在宅化)にオペレーターが抱える不安

管理者の視点で、コールセンター業務の在宅化に対する不安な点を解説いたしました。
同様に、実際にお電話で対応をするオペレーターの視点でも在宅化への不安はございます。
自宅のネットワーク環境
オペレーターの視点で多いのはネットワーク環境です。
管理者側としても、通信環境によるトラブルを懸念する声は多いのですが、オペレータ視点でも、職場では問題なく通信できていても自宅のネットワークで試したことが無いので不安、という方も多いです。
万が一に通信ができない状態になった際に、誰に聞けば良いかわかならい、という点も要因のひとつです。
同居人や家族への配慮
また、自宅で働く際には同居人や家族への配慮も必要となります。
家庭環境ではそれぞれのルーティンや生活がございます。
そこに普段とは異なる仕事の環境が加わりますので双方で気を遣う部分が出て参ります。
掃除や洗濯などの生活音や、家事をメインにしている方の休憩のタイミングなど、職場とは違った環境となります。
その他にも家族が暮らす中で、集中できる環境をどのように整理するのか、という心配もございます。
悩み事や不明点を聞くタイミング
職場では些細な質問であっても上司や管理者の方に質問する機会は多くございます。
仕事をしていると悩み事や不明な点も出てくるものです。
そんな時に、身近に質問できる人がいなくなるという点に不安を抱えるケースもあるのではないでしょうか。
そのような中ではモチベーションの維持などの課題へつながる可能性もでてきます。
顧客トラブルの際の対応
似たような話となりますが、顧客とのトラブルの際に一人で対応するのが不安、というケースもあるかもしれません。
職場であれば助けを求めることができても在宅の場合にどうしたら良いかわからず不安に思われる方も少なくないのではないでしょうか。
改善に近づく視点

以上のように管理者とオペレーターの双方で不安を抱える要因があり、コールセンター業務の在宅化が進まない要因となっております。
では、どのように不安な点を改善していけば良いのでしょうか。
マネジメントの観点とコミュニケーションの観点から見ていきましょう。
マネジメントの観点
まずはどのようにマネジメントを行うかという観点です。
必要な環境と、組織の在り方に整理することができます。
在宅コールセンターのマネジメントで必要な環境としては、オンラインで顧客を管理できるシステムやリアルタイムでフォローが可能な環境のふたつが重要です。
顧客の情報を共有し合って、どのような対応や進捗なのかが離れていてもわかるようにしなければなりません。
また、オペレーターの稼働状況などを押さえることができるツールでリアルタイムでモニタリングをしながら適時フォローが出来る必要もございます。
このような環境づくりは、コールセンターのシステムであれば実現できることがほとんどですので、在宅化でのマネジメントに関する不安がある場合は、一度ご確認いただければと思います。
次に、組織の在り方についても整理が必要です。
これまで時間報酬型でマネジメントしていたとするならば、成果報酬型へ切り替えるなどの見直しも必要です。
自立したオペレーターを育てることで在宅でもスムーズな運営をすることができます。
コミュニケーションの観点
改善に近づくためにはコミュニケーションの観点も欠かせません。
どのような運用やツールでコミュニケーションをとるのか、定期的な出勤によるケアを設けるのか、などコミュニケーションの方法を事前に検討しておく必要がございます。
非対面だと相手の気持ちがわかりにくくなる事を不安に思う管理者の方も多いかもしれません。
運用面でいえば、エスカレーションの方法を明示しておき必要な質問に答えるフローをつくっておくこと、事前にオフィスで試験運用しておくことが大切です。
コミュニケーション用のツールを用意しておき、組織のコミュニケーションを活性化させるのも良いでしょう。
改善に向けてやるべきこと

それでは以上のような改善の視点をふまえ、どのように在宅化を進めていくべきか、ポイントを整理してみましょう。
Step1:課題を明確化する
まずはじめに自社にとっての課題を明確にしましょう。
セキュリティ面、システム面、マネジメントやコミュニケーションの観点、など分類ごとに課題を整理しておき優先度を付けてみましょう。
優先度の高い課題に対しては必要に応じて対応できるツールを検討していく必要がございます。
次のステップに進むために、まずは課題を明確化することから始めてみましょう。
Step2:必要な機能を整理する
課題が明確になり、優先度を押さえることができたら、次は課題の解消に必要な機能を整理していきます。
セキュリティ面であればルールや規定を整理するのも大切ですし、情報漏えいに関する教育も大切です。
また情報セキュリティ技術についてシステム部門の方と対策を話し合っておきましょう。
コミュニケーションやマネジメント面の課題であれば、マニュアルの整備のほか、オペレーターの通話を同時に聞くことが出来る機能や、オペレーターへ適時アドバイスを発信できるような機能があると便利でしょう。
必要な機能を整理した上で、満たすことのできるツールを検討してみると良いでしょう。
Step3:比較検討
コールセンターを在宅化できるツールをいくつか比較していきます。
ここでは、導入にかかるコストの他、必要な機能を有しているのか、しっかりと押さえるようにしましょう。
安価で導入できたけれども機能が不足していては在宅化における課題を解消することができません。
Step2で整理した機能について一覧表にして比較検討してみるのもおすすめです。
Step4:スタッフの反応を見る
デモ環境などを用意できるのであれば実際に試してみておくのも良いでしょう。
そこでスタッフの反応を見たり聞いたりしながら、課題は解消できるのか、見えていない課題は無いのか、確認していくことができます。
コールセンターシステムはコールセンター業務の中心となるシステムです。機能の他にも使い勝手や品質など、いくつかの観点でスタッフの反応をうかがっておくようにしましょう。
Step5:社内調整
導入するツールを決定できれば実際に導入する為の社内手続きが必要となります。
その際には、システムを管理する部門や社内の電話などを管理している総務部門、営業への折り返しが必要なコールセンターであれば営業部門、など関連する部門との調整も必要です。
どのような部門にどのような点で調整していくのか、予め確認しておくと良いでしょう。
コールセンターのテレワーク(在宅化)には適切なツールの活用を!

コールセンターを在宅化するには、様々な不安や課題がございますが一つ一つを整理する事で必要な機能を明確にし、解決できるツールを探しやすくなります。
自社に沿った最適なコールセンターシステムを検討いただければと思います。
在宅コールセンターに対応できるクラウド型のコールセンターシステムでおすすめなのが「MOT/CallCenter」です。
インターネットとPCさえあれば在宅コールセンターを実現できます。
マネジメントに必要なリアルタイムモニターや通話録音、オペレーターの稼働管理画面も標準搭載。
さらに今ならキャンペーン利用で、オペレーターの雇用の際に便利な雇用契約書の電子化支援ツール「DX-Sign」もお得に使えます。ぜひこの機会に「MOT/CallCenter」をご検討ください。詳細は下記からご確認いただけます。
外部のサポートを活用してみる
在宅化に向けやるべきステップや適切なツールをご紹介しましたが、ノウハウがないまま自社だけで進めるのはなかなか難しいこともあります。そんな時は外部のサポートを頼ってみるのも手です。
コールセンターのテレワーク運営に不安を感じた時のために、最後におすすめのサポート先をご紹介します。
専門機関への相談
厚生労働省・総務省のホームページ「テレワーク総合ポータルサイト」では、テレワークを進めたいがどう行ってよいかわからないとお悩みの方へテレワークに関する役立つ情報を発信しています。
また、「テレワーク・ワンストップ・サポート事業」と称し、テレワークの導入を検討されている方が抱える様々な悩みについて電話やメール相談、セミナー開催などを通じたサポートも行っているようです。
コールセンター(コンタクトセンター)のテレワーク化に中々一歩が踏み出せないという方は、まずはこのような機関への相談から行ってみるのはいかがでしょうか。
コールセンターシステムの専用サポート窓口へ相談
いきなり専門機関へ相談するのは躊躇するという方は、コールセンターシステムを扱う専用のサポート窓口へ相談してみるのも手です。
「まだ導入するか検討していないのに相談しずらい」と思っている方もよくおられるのですが、当然、相談したからといって事業者は導入を強いることはできませんのでご安心ください。
最終的にツールを導入しなかったとしても、外部から色々な知識を得ることでテレワークを進めるべきか否か納得した決断ができますので、お悩みでしたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。
お問い合わせは以下から承っております。
まとめ
働き方が多様化している現代、在宅化のメリットを感じ導入を進めている企業も多いです。
そのような中、電子帳簿保存法の改正もあるため、書類を電子化したり契約書を電子化したりツールの検討を急がれる方も多いかと思います。
事業においてお客様と企業をつなぐ役割であるコールセンター業務は、性質上、在宅化がなかなか進まない分野でございましたが便利なツールによって構築できるようになってきております。
このようにDXを推進できるツールは、良質な人材の確保やBCP対策にもつながります。
また最近では、コールセンターの在宅化を進める中で、オペレーターの採用や更新で使用する雇用契約書の電子化も検討されるケースが増えてきました。コールセンターの在宅化に限らず、業務全般のDX化にもお悩みでしたらぜひ一度お気軽にご相談いただければと思います。